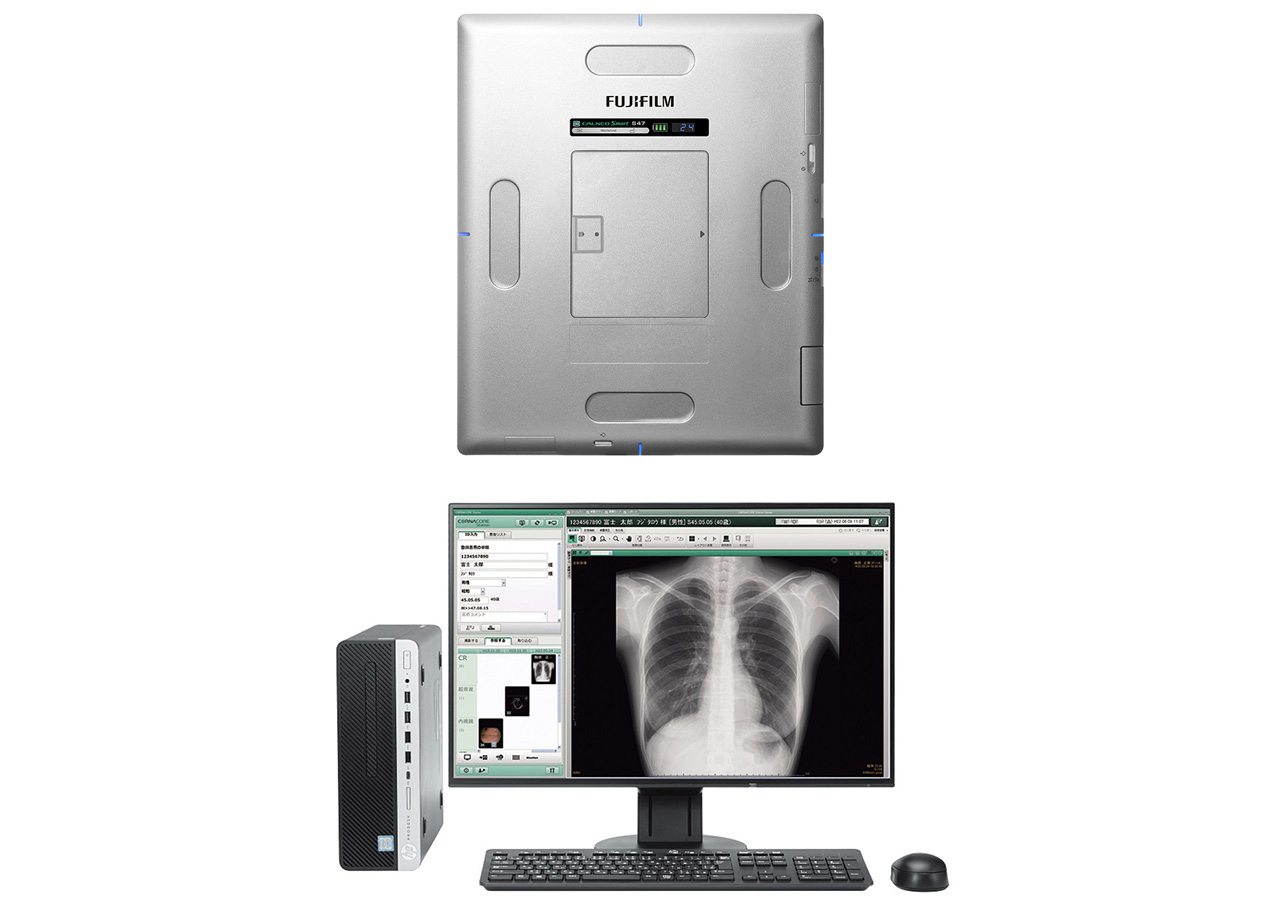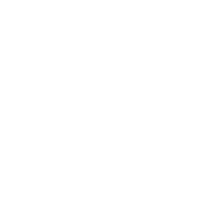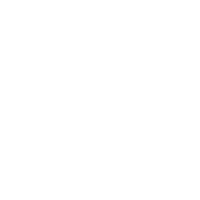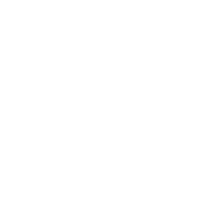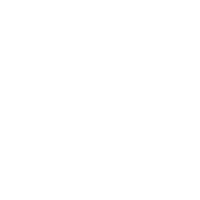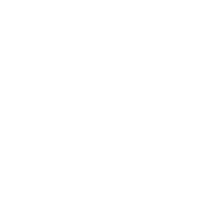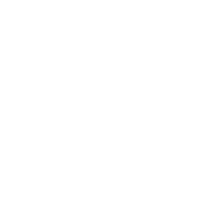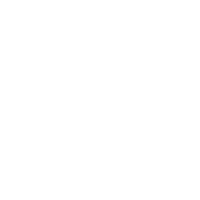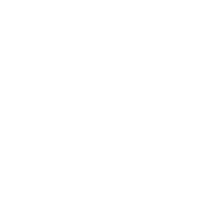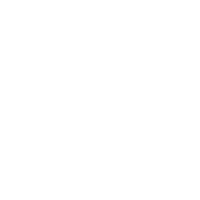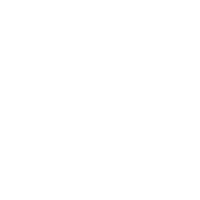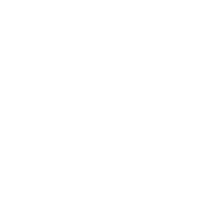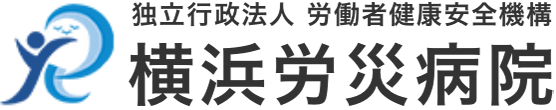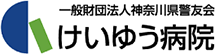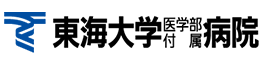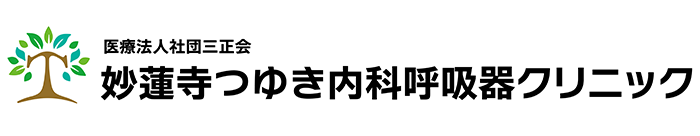2024.04.04(木)
新着情報
[ご予約に際してのご注意]
[ご予約に際してのご注意]
・当院はデジスマ払いには現在のところ対応しておりません。発熱・風邪症状外来は現金払いのみとなりますので現金のご用意をお願いいたします。
・一般外来のお支払いでクレジットカードやキャッシュレス決済をご希望の場合は「現金払い」を選択していただき、当日会計でお申し出ください。お手数をおかけしますがよろしくお願い申し上げます。